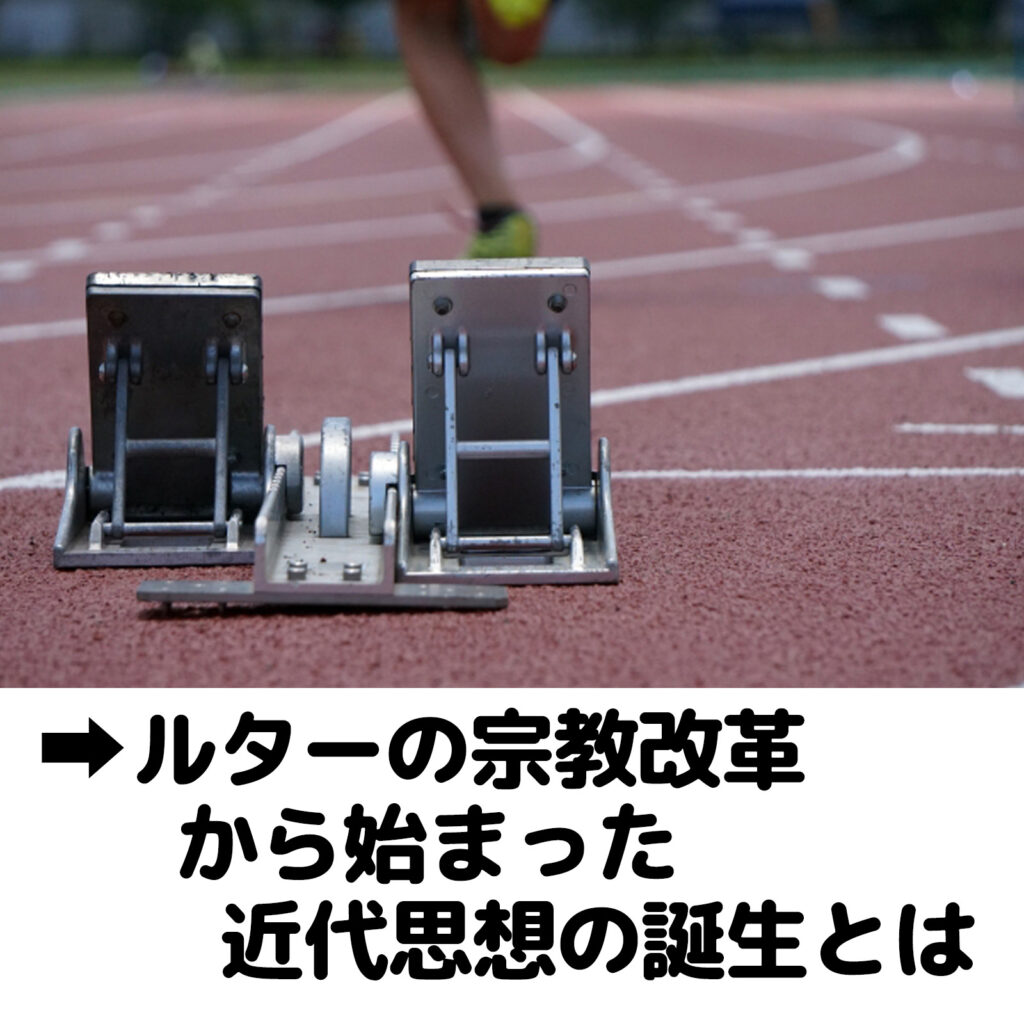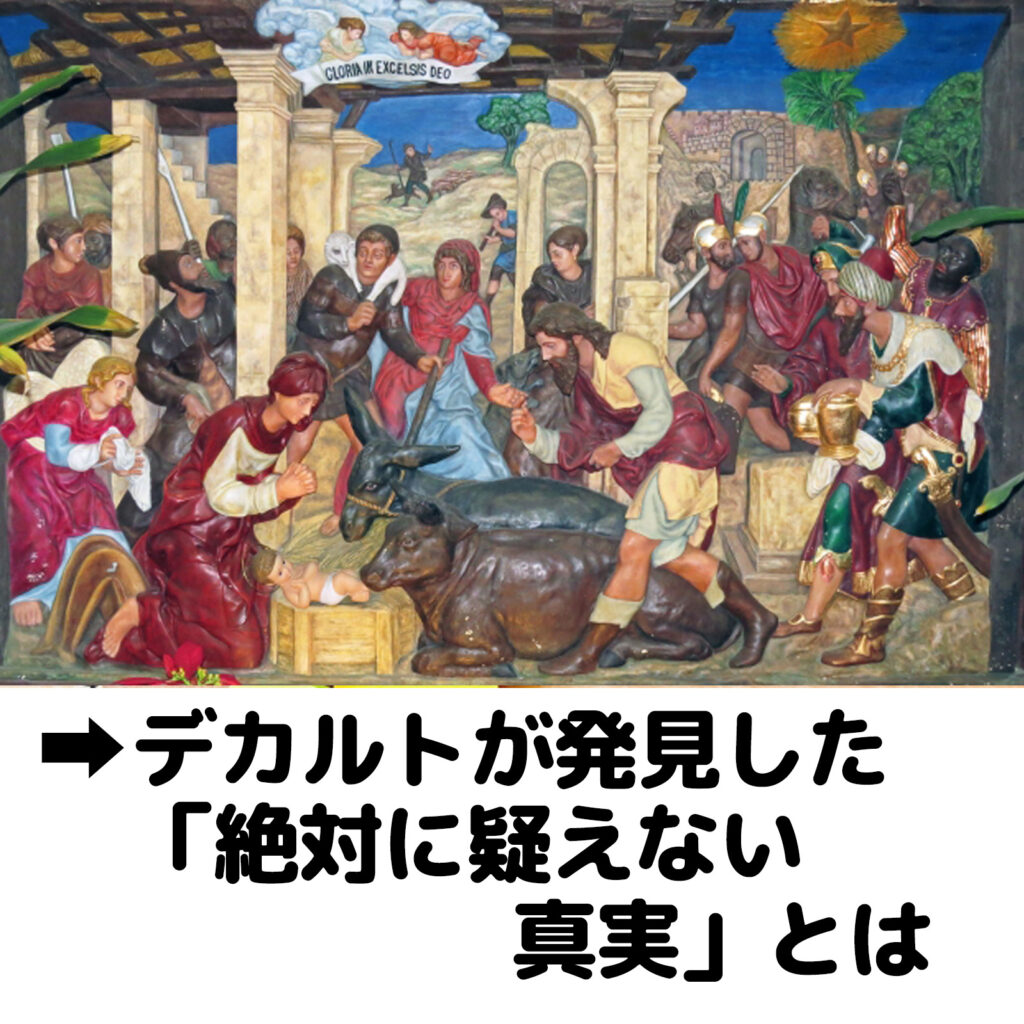デカルトが発見した「絶対に疑えない真実」とは
こんにちは。最近、哲学に興味を持ち始めた哲太です。「それって言う必要がありますか?」が口癖のくせ者です。
今回もデカルトについて解説していきます。
皆さんは、目の前のコーヒーカップを見て「これは本当に存在するのかな?」と考えたことはありますか?
「そんなこと考えなくても、目の前にあるんだから存在するに決まってるじゃない!」と思われるかもしれません。でも、デカルトは「それすら疑ってみよう」と考えた、とても大胆な哲学者だったのです。
前回のまとめ

前回は、デカルトが考え出した4つのルールについてお話ししました。
そのルールは「明証性」「分析」「総合性」「枚挙」という4つの規則でした。
これらは現代のビジネスでも活用されている、とても便利な考え方です。今回は、デカルトがその4つのルールを使って発見した「絶対に疑えない真実」について、くわしくお話ししていきましょう。
「我思う、ゆえに我あり」はこうして生まれた! 〜とことん疑い抜いた先にあったもの〜

デカルトは「どこからどう見ても真と認められるモノ以外は受け入れない」という、1つ目のルール(明証性の規則)を、徹底的に実践してみることにしました。
まず、目の前にあるコーヒーカップ。
「これは本当に存在するのだろうか?」
とデカルトは考えました。
もしかしたら、私たちは幻覚を見ているだけかもしれません。実際、夢の中では「確かにあると思ったもの」が、目が覚めたら「実は存在しなかった」ということが、よくありますよね。
デカルトはさらに考えを進めていきました。
「1+1=2」という、誰もが正しいと思っている簡単な計算でさえ、もしかしたら間違っているかもしれない。人間は不注意で計算を間違えることがあるからです。
このように、デカルトは「少しでも疑える可能性があるものは、いったん全部疑ってかかろう」と決意したのです。
この「とことん疑ってみる」というデカルトの方法を、私たちは「方法的懐疑(ほうほうてきかいぎ)」と呼んでいます。懐疑というのは「疑う」という意味です。
普通の人なら「そこまで疑わなくても……」と思うようなことまで、デカルトは徹底的に疑い続けました。
そして、すべてのものを疑い続けた末に、デカルトはある重大な発見をします。
「今、こうして私が疑っている」という事実だけは、絶対に疑うことができない。なぜなら、「私は疑っているのだろうか?」と疑うこと自体が、「私が疑っている」という証拠になってしまうから。
この発見から、デカルトは有名な言葉を残しました。
「我思う、ゆえに我あり」
(フランス語では「Je pense, donc je suis ジュ・パンス・ドン・ジュ・スイ」)です。
つまり「私は考えている、だから私は確かに存在している」という意味です。
この考えは、どんな反論も受けつけない「絶対に正しい第一の真理」として、デカルトの哲学の土台となりました。そして、この発見は人類の考え方を大きく変えることになったのです。
デカルトの「我思う、ゆえに我あり」という発見は、もう一つの重要な考え方を生み出しました。
それが「心身二元論」という考え方です。
デカルトは、人間は2つの要素でできていると考えました。
1つは「考える心(精神)」、もう1つは「体(物体)」です。先ほどの「方法的懐疑」で、デカルトは体の存在さえも疑いました。でも、「考えている自分」だけは疑うことができなかったのです。
このことから、デカルトは「心と体は別のもの」だと考えました。
この考え方のおかげで、科学はさらに大きく発展することになります。なぜなら、人間の体を「物体」として研究することが、道徳的に認められるようになったからです。
当時のヨーロッパでは、人間の体を研究することは「神様が作った大切なものを傷つける」として、よくないことだと考えられていました。でも、デカルトの「心身二元論」によって、体は「物体」として研究できるようになったのです。
デカルトはなぜ神の存在を証明しようとしたのか? 〜知られざる歴史的背景〜

さて、ここまでデカルトの素晴らしい発見についてお話ししてきました。でも実は、デカルトには大きな悩みがありました。
それは「この考え方を、どうやって世の中に広めるか」ということです。
デカルトが生きていた17世紀のヨーロッパでは、カトリック教会がとても強い力を持っていました。新しい考え方を発表すると、「神様に逆らっている」として罰せられることもあったのです。
実際に、デカルトが『方法序説』を書く4年前、有名な科学者のガリレオ・ガリレイが教会から裁判を受けました。ガリレオは「地球が太陽の周りを回っている」という正しい説を唱えましたが、それが「聖書の教えに反する」として罰せられてしまったのです。
デカルトは、この出来事を聞いてとても心配になりました。
実は彼は、『世界論』という本を書き終えていたのですが、ガリレオの裁判を知って出版を取りやめてしまいました。そして、自分の考えを世の中に広めるために、ある工夫をすることにしたのです。
それが「神様の存在証明」でした。
デカルトは『方法序説』の中で、「人間は不完全な存在です。完全な神様のことを考えることはできません。だから、完全な神様は確かに存在するはずです」というような説明をしています。
この説明は、それまでのデカルトの「徹底的に疑う」という姿勢からすると、少し違和感があります。実際、当時の哲学者パスカルは「デカルトは本当は神様なしで済ませたかったのに、仕方なく神様の話を入れたのだろう」と批判しています。
デカルトが神の存在証明を行ったのは、おそらく「処世術」、つまり世の中をうまく渡っていくための知恵だったのかもしれません。
実際、デカルトは『方法序説』の中で「思い違いをしているかもしれないと心配になって、『世界論』の出版は見送った」と正直に書いています。
その一方で、デカルトは「でもこの4つのルールを使えば、何が正しいかは自然とわかるはずだよね」とも書いているのです。
これは、まるで「本当のことを知りたければ、私の4つのルールを使ってみてください」と、読者に向かってヒントを投げかけているようにも読めます。
また、デカルトは、自分の考えを説明している人について「正しく理解していない」とも言っています。そして「私が書いたもの以外は信じないでください」とまで述べているのです。
これは、デカルトが当時の状況の中で、とても慎重に自分の考えを伝えようとしていた証拠かもしれません。
このように、デカルトは時代の制約の中で、できる限り真実を追求し、それを後世に伝えようと努力しました。
その結果、科学は大きく進歩し、私たちの考え方も大きく変わることになったのです。
デカルトの「すべてを疑ってみる」という姿勢は、現代を生きる私たちにも大切なことを教えてくれています。「これって本当に正しいのかな?」と立ち止まって考えることは、新しい発見への第一歩となるかもしれないからです。
このように、400年以上前に生きたデカルトの思考法は、今でも私たちの生活やビジネスに活かすことができる、とても実践的な知恵といえるでしょう。
まとめ

デカルトの残した大きな功績は、主に2つあります。
1つ目は、「明証性」「分析」「総合性」「枚挙」という4つの思考ルールです。
これらのルールは、科学の発展を促しただけでなく、現代のビジネスの世界でも活用されています。たとえば、マクドナルドの100円コーヒー戦略のように、複雑な問題を解決するための道具として、今でも役立っているのです。
2つ目は、「すべてを疑ってみる」という姿勢です。
デカルトは、当たり前だと思われていることでさえ、徹底的に疑ってみることで、「我思う、ゆえに我あり」という揺るぎない真実を発見しました。この発見は「心身二元論」という考え方を生み、科学の発展に大きく貢献しました。
デカルトは、強大な力を持っていた教会との関係に悩みながらも、できる限り真実を追求し、それを後世に伝えようと努力しました。その結果、科学は大きく進歩し、私たちの考え方も大きく変わることになりました。
「これって本当に正しいのかな?」と立ち止まって考えること。そして、複雑な問題を小さな部分に分けて、順序立てて考えていくこと。
デカルトが教えてくれたこれらの考え方は、400年以上の時を超えて、今を生きる私たちの生活やビジネスにも、大きな示唆を与えてくれているのです。
【参考資料】
「方法序説」
「パンセ」
「世界のエリートが学んでいる 教養書必読100冊を1冊にまとめてみた」(KADOKAWAオフィシャルサイト)
あわせて読みたい記事
※このブログは、神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」の哲太が執筆しました