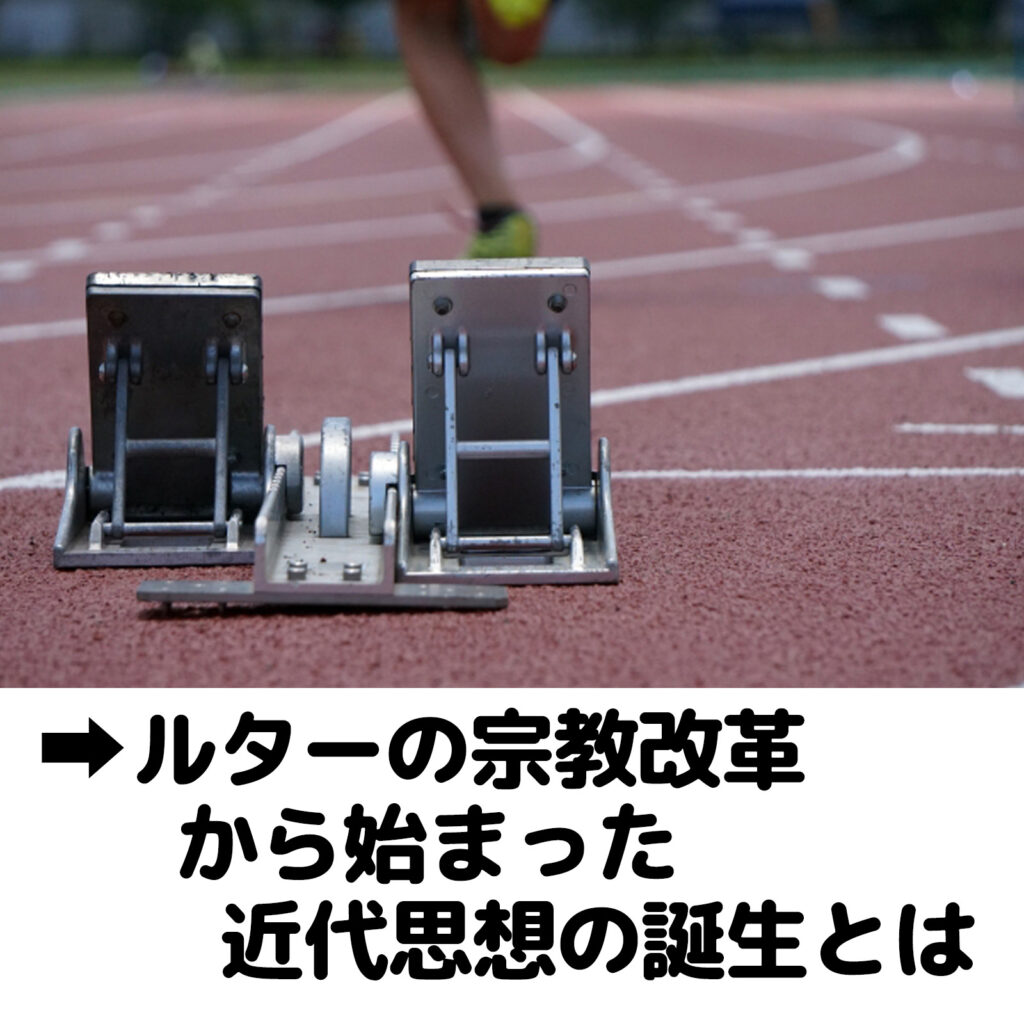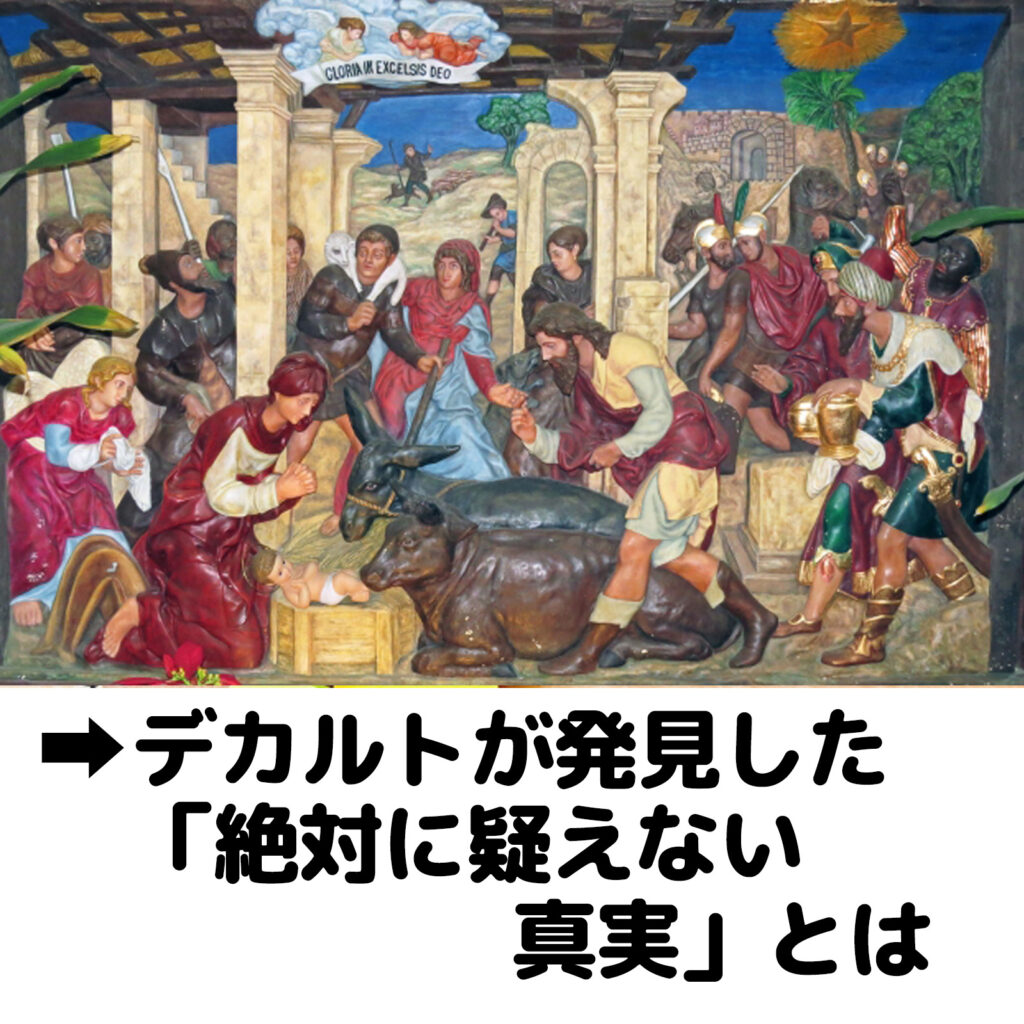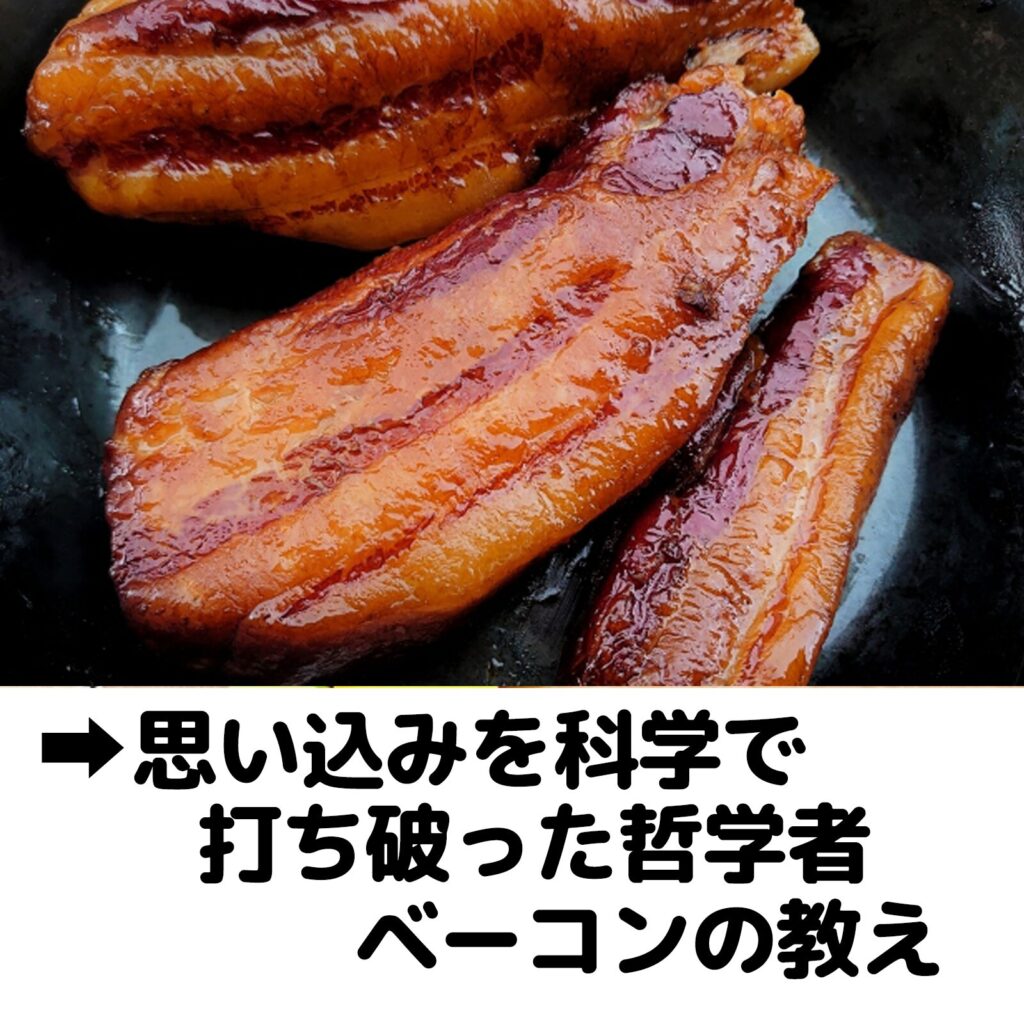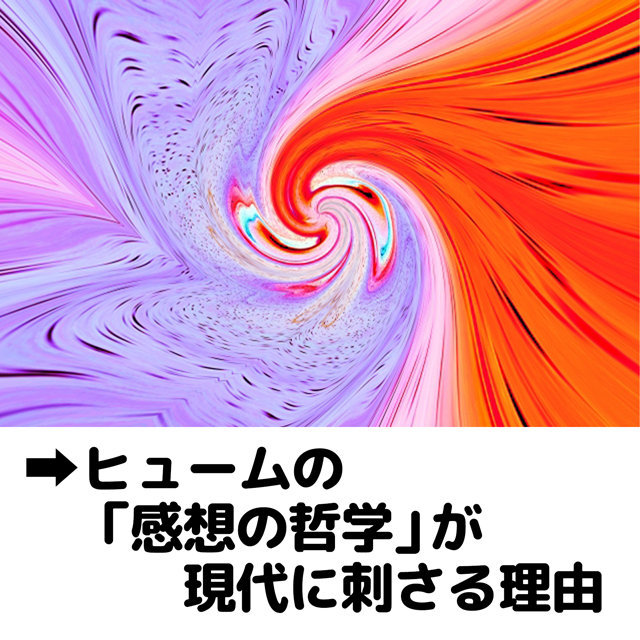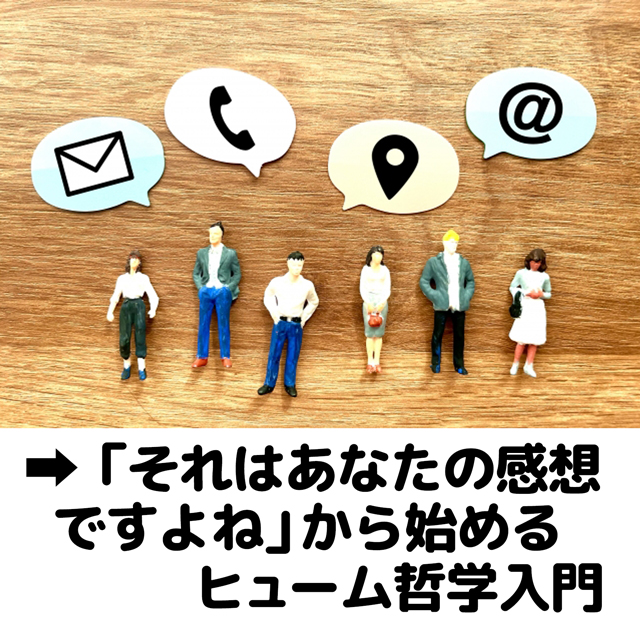真実を見抜け! ベーコンが警告した4つの思い込みとは
こんにちは。最近、哲学に興味を持ち始めた哲太です。「それって言う必要がありますか?」が口癖のくせ者です。
今回も引き続き、ベーコンについて解説していきます。
私たちの身の回りには、さまざまな情報があふれています。
SNSやメディアを通じて次々と入ってくる情報の中から、どうやって真実を見分ければよいのでしょうか。前回は、科学的思考の父と呼ばれるフランシス・ベーコンの基本的な考え方について学びました。
前回のまとめ

科学革命期に活躍したベーコンは、アリストテレスの三段論法では新しい真理は見つけられないと指摘しました。
そして、具体的な事実から法則を導き出す「帰納法」を提案。
ただし、単に事実を集めるだけでなく、ミツバチのように集めた材料を加工して新しい価値を生み出すことが大切だと説きました。
ベーコンが警告した「4つのイドラ」とは?

ベーコンは『ノヴム・オルガヌム』の中で、人間の思考を妨げる4つの先入観について警告しています。
これを「イドラ(偶像)」と呼び、
「真の帰納法のためには、4つのイドラを排除すべきだ」
と主張しました。
最初のイドラは「種族のイドラ」です。これは人間の本性に根ざした錯覚のことを指します。
たとえば、私たちは目の前の小さな損失を避けたがる傾向があります。「ワクチンは副反応があるって聞いたので怖いです」という考えは、まさにこの種族のイドラの典型例です。
2番目は「洞窟のイドラ」です。これは個人の経験だけに基づいた思い込みのことを指します。
「自分の周りには感染者がいないから、マスクと消毒だけで大丈夫」という考え方は、まさにこの洞窟のイドラの例です。自分の限られた経験だけを基準にして判断してしまうと、より広い視野での真実を見失ってしまう危険があります。
たとえば、新型コロナウイルスの感染者数は、2020年から2023年までの間で大きく変動していました。厚生労働省の発表によると、感染の波には地域差もあり、また無症状の感染者も多かったことが分かっています。
つまり、「周りに感染者がいない」という個人的な観察だけでは、本当の感染状況は把握できないのです。
3番目は「市場のイドラ」です。これは、社会生活の中で伝聞により生じる思い込みのことです。
前回触れた「ワクチンにマイクロチップが仕込まれている」という噂は、この市場のイドラの典型例です。
このような噂が広がる背景には、SNSの影響力の強さがあります。実際、2021年に米国で行われた調査では、約7%の回答者が「ワクチンには追跡用チップが含まれている」と信じていたことが報告されています。これは、正確な情報源を確認せずに、SNSでの投稿を鵜呑みにしてしまった結果と言えるでしょう。
そして4番目が「劇場のイドラ」です。これは、権威ある人物や組織の発言を無批判に受け入れてしまう思い込みのことです。
「ワイドショーで○○さんが『遺伝子情報が書き換えられる』と言っていた」という考え方は、この劇場のイドラの典型例です。
実際、新型コロナワクチンに関して、遺伝子の書き換えを懸念する声がありました。しかし、厚生労働省は科学的な根拠に基づいて、「mRNAワクチンは遺伝情報であるDNAを書き換えることはない」と明確に説明しています。
【参考】
新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)
テレビに出演する著名人の発言であっても、その分野の専門家でない場合は、発言の根拠を慎重に確認する必要があるのです。
現代の科学的思考とイドラの克服

ベーコンが指摘した4つのイドラは、現代の行動経済学でいう「認知バイアス」に非常によく似ています。
認知バイアスとは、人間の判断や意思決定を歪めてしまう心理的な傾向のことです。
たとえば、「確証バイアス」は、自分の信念や仮説に合う情報ばかりを集めてしまう傾向を指します。これは、ベーコンの言う「洞窟のイドラ」に近い概念です。
また、「権威バイアス」は、権威ある人物の意見を過度に信頼してしまう傾向を指し、「劇場のイドラ」と重なる部分が多くあります。
現代に活きるベーコンの教え

ベーコンの指摘した問題は、400年以上経った現代でも極めて重要な意味を持っています。むしろ、情報があふれる現代だからこそ、より一層その重要性が増していると言えるでしょう。
たとえば、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する議論は、2023年に入って新たな展開を見せています。ウイルスの弱毒化に伴い、科学者たちは「ワクチン接種の副反応リスク」と「感染時の重症化リスク」を、データに基づいて比較検討するようになりました。
これは、まさにベーコンが提唱した科学的アプローチの実践例と言えます。個人の経験や噂、権威者の意見に頼るのではなく、実際のデータを収集・分析し、そこから結論を導き出そうとする姿勢です。
もちろん、現代の科学は、ベーコンの時代よりもはるかに進歩しています。20世紀に入ってからは、統計学や因果推論といった新しい方法論も発展してきました。
これらの手法を使えば、より正確に真理に近づくことができます。
しかし、その基礎となる「先入観を捨てて、事実から考える」という姿勢は、ベーコンが提唱した考え方そのものなのです。
まとめ ~科学的思考で真実を見極めよう~

ベーコンが私たちに残してくれた最も重要なメッセージは、
「4つのイドラを排除し、帰納法で考えよ」
という教えです。
これは、科学的思考の基本として、現代でも極めて重要な意味を持っています。
では、私たちは日常生活の中で、どのようにしてこの教えを実践できるでしょうか。以下の3つのポイントを意識することから始めてみましょう。
- 1つ目は、自分の思い込みを常に疑ってみることです。「なぜ私はそう考えるのか?」と自問自答することで、4つのイドラの影響を減らすことができます。
- 2つ目は、情報源を必ず確認することです。特にSNSやインターネットの情報は、その出所と信頼性を慎重に確かめる必要があります。
- 3つ目は、複数の視点から物事を見ることです。ベーコンが言うように、ミツバチのように情報を集めて加工し、新しい価値を生み出す姿勢が大切です。
現代社会では、フェイクニュースや誤情報が瞬く間に広がってしまいます。しかし、ベーコンの教えを実践することで、私たちは真実により近づくことができるんです。
ベーコンは「知識は力なり」という言葉も残しています。
正しい知識を得るための科学的思考法を身につけることは、私たち一人一人が真実を見極め、より良い判断を下すための重要な「力」となるはずです。
【参考資料】
「ノヴム・オルガヌム」(岩波書店)
「世界のエリートが学んでいる 教養書必読100冊を1冊にまとめてみた」(KADOKAWAオフィシャルサイト)
あわせて読みたい記事
※このブログは、神奈川県横浜市にある就労継続支援A型事業所「ほまれの家横浜」の哲太が執筆しました